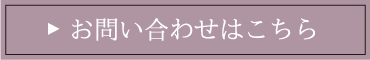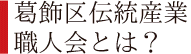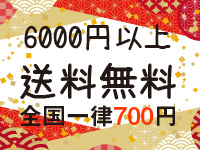菊和弘

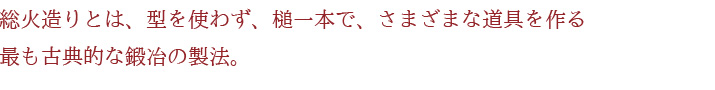
父親の享幸氏の跡を受け継ぎ、菊和弘の工房を一人で切り盛りするのが康宏氏だ。
裁ち鋏の名匠として、全国的に名をはせた享幸氏の跡を受け、さぞかし、重圧もあったのではないかと思うが、意外にもそうした気負いはご本人からは感じない。 むしろ、自分自身もいつかは父のように、あらゆる刃物を作ってみたいと楽しそうに意気込みを語る。
「鋏は難しいんですよ。今は納得のいくものできるように一生懸命、修行中です」と大河原さんは笑う。
修行中と控えめにご本人はいうが、令和元年に葛飾区の厳しい選考基準をクリアし、認定されたれっきとした伝統工芸士である。葛飾区伝統産業職人会においても、若手ながら中心のまとめ役として、区のイベントなどの取りまとめ役をこなしている。
その実直な人柄と、自由な発想で生み出される新たな製品が注目され、全国の百貨店から展示会へのオファーが絶えない。
裁ち鋏の名匠として、全国的に名をはせた享幸氏の跡を受け、さぞかし、重圧もあったのではないかと思うが、意外にもそうした気負いはご本人からは感じない。 むしろ、自分自身もいつかは父のように、あらゆる刃物を作ってみたいと楽しそうに意気込みを語る。
「鋏は難しいんですよ。今は納得のいくものできるように一生懸命、修行中です」と大河原さんは笑う。
修行中と控えめにご本人はいうが、令和元年に葛飾区の厳しい選考基準をクリアし、認定されたれっきとした伝統工芸士である。葛飾区伝統産業職人会においても、若手ながら中心のまとめ役として、区のイベントなどの取りまとめ役をこなしている。
その実直な人柄と、自由な発想で生み出される新たな製品が注目され、全国の百貨店から展示会へのオファーが絶えない。


▲研ぎは中砥石と仕上げ砥石の二種類。特別なことはしていないというが、あまりの切れ味に、研ぎの依頼も絶えない


 ▲すべて手で打ち出した出刃包丁、三徳包丁、柳刃包丁
▲すべて手で打ち出した出刃包丁、三徳包丁、柳刃包丁

■大河原康弘氏の三徳包丁の作り方、製作工程がご覧いただけます ※音が出ます
4件の商品がございます。